・最近足が疲れやすくて思っているように足が上がらない
・ちょっとした段差でつまずき転んでしまった
老化により筋力や関節可動域の低下が起きるとこのようなお悩みが増えてくると思います。
この記事では、高齢者が転倒しやすい原因や靴選びのポイント解説していきます。
目次 [hide]
高齢者が転びやすい原因
原因は大きく分けると2つ。内的要因と外的要因です。
内的要因は、老化や病気による身体機能の変化、また服薬による副作用などが挙げられます。
関節の柔軟性や筋力の低下、視力の低下など、様々な要因がその人のバランス機能の低下を助長します。
外的要因とは段差などの障害物や滑りやすい床など、その人をとりまく環境です。
対策としてのおすすめは、介護保険を使用した住宅改修サービスの活用です。
補助金が利用できるうえ、改修項目には手すりの取り付けや段差解消、床材変更などが含まれています。
制度を活用し、その人にあった生活環境を整えることも外的要因を取り除く方法の一つです。
そういった意味では、その人に適さない靴を履いていること自体が、大きな外的要因であると考えられます。
転びやすい靴の特徴①~サイズの合わない靴~
靴のサイズを決める要素は3つあります。
・足長 ・足幅 ・足囲
足長とは、踵の先端から一番長い足趾の先端までを結んだ距離です。いわゆる靴のサイズとはこの長さを言うことが多いかと思います。
皆さんも靴を選ぶときにこのサイズ(足長)を確認して靴屋さんで購入を検討されているでしょうか?
しかし、しばしば経験することとして、実際に履いてみるとつま先がきつく感じたり、踵が緩く感じることもあると思います。
これはその人の足幅や足囲を考慮しないため、実際の足の形に合わないものを履くことで起きる現象です。
このように足のサイズに合わないものを普段から履くと、痛みが出たり痛みを避けようとして本来の歩き方から逸脱する可能性もあります。
転びやすい靴の特徴②~つま先が十分に曲がらない靴~
つま先が曲がりにくい靴も、足の振り出しが十分に行えずにすり足となってしまう原因となります。
効率的な歩行では、踵が離れていくタイミングで足趾の関節が伸展して足裏(足底腱膜)が程よく牽引されます。
これにより足底腱膜に張力が発生し足のアーチが巻き上げられ足部の剛性が向上します。
また、この張力が床に対して反発する力を生み出すことで、足を大きく前に蹴りだすことができるのです。
そのため、つま先が曲がらない靴は足趾の伸展を阻害して足の振り出しがうまく行えなくなってしまいます。
転倒を予防する靴選びのポイント① 足幅と足囲を考慮したサイズ選び
先ほど記したとおり、足のサイズは足の長さだけでは決まりません。
足長に対する足幅・足囲(ワイズ)の状態によって決まります。
日本産業規格(JIS規格)より、このワイズはA・B・C・D・E・2E・3E・4E・5Eと数字が増えるほどに足幅が広くなります。
施設や病院でもよく見かける徳武産業様のあゆみシューズ、なかでも「ダブルマジック」シリーズはなんと11Eまで選べます。
足のワイズは立っている姿勢(荷重下)と座っている姿勢(非荷重下)で大きさに差がある方もいます。
また、病気による浮腫みや足趾の関節変形足等により、足長だけで選ぶと靴のワイズ狭く窮屈に感じてしまうことも多くあります。
購入の前にこの「ワイズ」を図ることで、より身体に合った靴を選ぶことができるでしょう。
転倒を予防する靴選びのポイント② 足のアーチを保つもの
土踏まずが減っているいわゆる「扁平足」という状態は、靴の幅が広くサイズの合っていない靴を履いていても起こります。
また、運動不足や加齢による筋力の低下によっても足のアーチが崩れ、扁平足を助長します。
足のアーチ(いわゆる土踏まず)は横アーチと内側・外側縦アーチの計3か所で構成されています。
なかでも内側縦アーチを保つ筋肉は主に4つです。
・前脛骨筋 ・後脛骨筋 ・長拇趾屈筋 ・長趾屈筋
これらの筋肉は足の裏を走っており、足のアーチが落ちないように支えています。
しかし、アーチが崩れれば足趾の把持力が低下し、バランスがとりにくくなるため、転倒の危険性が増加します。
そのため、足のアーチを支えて土踏まずを高く保つことのできる靴選びが、転倒の予防では重要です。
そのほか市販の中敷き(インソール)でアーチを高めることもできるので、まずは100均ショップを探すのもオススメです。
※※当記事には、アフィリエイトプログラムを掲載しています。
転倒を予防する靴選びのポイント③ つま先が曲がりやすいorトゥースプリングがあるもの
既にお伝えしたように、つま先が曲がりにくい状態は足底腱膜の張力がうまく発揮されず、足の振り出しを弱めてしまいます。
そのため、購入する前に実際に靴を試し履きできるのであれば、つま先が十分に曲がるか手に取って確認しましょう。
また、靴の形状によっては、つま先が床から離れて持ち上がっているものがあります。
この床から持ち上がったつま先部分のことをトゥースプリングと呼びます。
トゥースプリングがあることで前足部への荷重を円滑にし、足の振り出しを容易にすることができます。
このトゥースプリングは、過度な高さの場合に本来の足の機能を低下させるという説もあるため、高すぎないものを選びましょう。
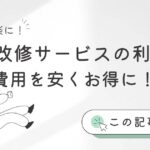
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ea27576.b960e495.3ea27577.26883c6f/?me_id=1311866&item_id=10002564&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fys-factory%2Fcabinet%2Fgoods%2F20230729sg-01_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
